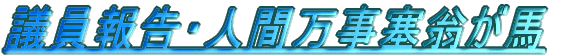
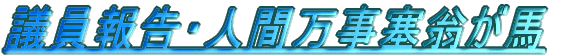
| ブログ選挙(立候補から落選までの軌跡) |
2019年統一地方選挙赤井川村議員選挙に立候補した際インターネットのブログに書いた村への思いを一ページにまとめました。結果は落選。やり方が悪かったということでしょう。本文にもありますが、挑戦することに負けはなしで、いい経験になりました。長文ですが僕に軌跡として宜しければお読みください。 ***************** 始まり ************************ 新年号が『 令和 』に決まりましたね。新たな時代の幕開けです。 時代の変化も複雑で多様性を求める時代ですが、僕も新たなる決意をしましたのでご報告します。 4月16日に告示される赤井川村議会議員選挙に立候補します。 このブログは僕の日常をお伝えする目的に立ち上げたもので、一日平均200ぐらいの訪問者がいます。 その多くが野菜の購入者だったり、フェイスブックのお友達だったり、以前から我が家を応援して頂いている貴重な方々だと思いますが、今日から少し趣旨を外れ、選挙当日の21日までの間、このブログを通し、村に対する思いと、選挙にかける思いをお伝えしていくことをお許しください。 少し重たい話題なので、一日おきに2・3分で読めるものをにしたいと考えていますので、是非、多くの人達に読んでもらいたいと思います。 出るか?出まいか?ずいぶん悩みました。 軟弱な精神力なので、落選したときのダメージばかりを考え、「出る必要ないんじゃないの?」と、僕の肩を掴むもう一人の自分がいて、何度も向き合いました。 でも、今回は「出る」ことで、自分の中にあるいくつかの疑問にも答えを出すことができると、決意しました。 当選するかどうかはまったく予想もできませんが、自分らしく選挙を戦いたいと思います。 そもそも何故立候補するかと言うことですが、 一番はこの村に対する愛です。 「村を愛する」と言う言葉は、少し滑稽に思えるかも知れませんが、僕は25年前、都会を離れて自分の意志でこの村に住み着きました。 子育てをテーマに田舎暮らしを志し、この足で北海道の各地を回り、多くの場所から自らこの村を選択したのです。 だからこそ、この村に対する思いはとても強いし、この村の将来についても、あれやこれやと思いを馳せています。 そんな僕の思いと、最近の村の進んでいる方向に大きなズレを感じています。 「おいおい、、、」とか、 「ええええぇ〜」って思うことが多くなって、、、。 どこにでも文句を言う人はいます。 大多数はそうでしょう。人はそんなに強くないから、小さい声で、人に聞かれないぐらいの小さな声で叫ぶものかも知れません。 昨日までは僕もその一人でした。 でも、そのままにしておくと、この村が嫌いになりそうだから今回立候補する準備に入りました。 「なにを青臭いこと言ってんだ!」と笑う人もいるでしょう。 でも、そうやって今まで青臭く赤井川村で25年やってきました。 だから、今回も僕らしく、あくまで正攻法でいきます! 21日まで、このブログは赤井川村民に向けてのものとなりますが、 多くの方にご覧いただき、ご感想など頂ければ幸いです。 と言うことで、今日は報告まで。 情報は送り手と受け手の思いがマッチしているかどうかが一番の課題だ。受け手が多くなればなるほど表現の方法は難しくなる。興味のない人に興味のないことをひつこく言い続けてもダメだし、趣味が合えば、ひとつの事を伝えただけで情報がドンドン膨らむこともあるのだ。 議員になったら、効果的な村の情報発信に努めたいと思う。僕の目線で、見たり、聞いたり、感じたことを紹介していく。 ――――――「わからない、知らない」からのスタート。 あくまで新人らしく、議会の質疑の様子や、行政の考え、日頃感じた「どうなっているの?」という疑問に対し、精一杯向き合い情報発信するつもりだ。(選挙公約:議員報告) ―――ひとつ例をあげる。 今年赤井川村開村120年、それを祝う行事があるのはご存知でだろうか? 「そもそも、なんで120年なんだろうか・・・?」(笑)僕が赤井川村に移住して25年。開村100周年の式典には参加させてもらったが110年を祝う行事はなかったと記憶している。120年と言う数が、縁起の良い節目としてやる意味がわからなくもないが、他市町村でも開村120周年を祝っているのか、、、これは調べてみる価値がありそうだ。 既に開村120年記念行事実行委員会というのがあるらしく、取り組みが先日配られた4月の広報に紹介されている。(余談だが120本の桜の苗木を植える行事があり、将来その桜の木の下で全村民が集いお花見をする企画があれば是非参加してみたい) ただ、わかりづらいのはその次の予算 聞いた話ではその行事の予算総額が約4000万円だということ。 4000万円の詳しい内訳までわからないが、一番驚いたのは1500万円を超える馬鉄のモニュメントができること。 人口約1000人のこの村。今回のイベントをひとりあたりに換算すると約4万円。モニュメントはひとりあたり15000円、4人ひと家族では、なんと6万円の出費相当になるのだ。 このイベントがこの村の身の丈にあったものなのか・・・?個人的には甚だ疑問だ。 ―――大切なのはここから。 既に色んな所で議論され、決まったことを今更蒸し返しても仕方はない。 でも、問題はそのイベントの経緯や経過がまったくわからないこと。見落としがないことを祈るが、僕が見た4年分の広報とHPには120周年の記念イベントの話題は見当たらなかった。それこそ、実行委員はどうやって募集し、モニュメントのデザインの募集や選定方法はどうやったのか・・・?それとも誰かの一存で動いているの・・・? もしかすると知らないのは僕だけ?なんて思ってしまうほど話が進んでいるので、何人かの知人に聞いてみたが、まったく回答が得られなかった(議員も知らないの?) だから立候補する。 わからないこと、知らないこと、それを教わりに行くのです。そして、なるべく多くの方に伝わるようにしたい。 全ての情報を開示すれば良いとは思っていない。 必要なのはマッチすること。もう少し分かりやすい情報の公開の仕方はあるはず。 村の広報に年4回「議会だより」が掲載される。色んな意見があると思うので「どうしたら良い」と言う議論はここではやらないが、もう少し住民目線の情報公開がなされていれば変な噂やデマが飛び交うことはない。 議員の皆様は、支援者に議会報告をしているのだろうか? 分からない間に、知らない間に、不必要だと思える建物や、イベントがあれば、 「あれは一体なんだ?なんかおかしいぞ」って言うのですよ!住民は、、、。 骨のいる作業かも知れないが、支援者の為に骨を折る(汗をかく)覚悟で議員になったのではないのだろうか?僕は唯一の選挙公約として議員報告をすると決めた。なるべくわかりやすい報告をしたいと思う。 付録:約1時間『開村120年』を基に色んな言葉でネット検索してみた。一杯120年の記念式典情報が出てくるかと思ったがほとんど見当たらない。ますます調べてみる必要がありそうだ。 このブログはスマホで見ているだろうか?それともパソコンだろうか? ガラケーを使っていた頃は「電話とメールができれば充分!」なんて思っていたが、スマホを持つとまったく生活の質が変わる。上手い表現だとは思わないが「時間軸」が変わったような錯覚になる。 僕ら世代、つまり団塊世代が産んだ子供たちは経済成長の真っ只中。良い高校に行って、良い大学に行って、大手企業に就職することが幸せだと教えられた世代だ。 晩御飯を食べ終えると8時から11時までは机に座って勉強をするわけですよ。「集中しなさい」なんてお袋に叱られながら、、、。だから、時間は垂直軸にひとつひとつをコツコツと積み上げるものだった。 ―――――それがどうだろう。 今ではスマホでメルカリ見ながらテレビでドラマ、次々に入ってくるラインの着信音でメッセージに目をやり、ドラマがコマーシャルになると天気予報を見たり夕食に食べた食事のカロリー計算までする。そのぐらいの事は50を過ぎた僕でもやってるし、最近はスマホでゲームと読書も覚えたので、病院の長い待合室もまったくイライラすることがない。 今のスマホ世代(若者)は、もっと凄くて、フリックス(文字入力方法)は当たり前だし、YouTubeで短い動画を次から次へと斜めに見ることができるらしい。 つまり、僕が実践してきた垂直的な時間の軸は崩壊し、良い悪いのロジックはおいといて、平面軸で物を見たり、同時に多くの行動をしなければいけない。 そんな多元行動は物事が進むスピードを上げる。今、社会が求められる活性化とは、そのスピードに対応する能力ではないだろうか? ―――――もう少しスマホの話を続ける。 スマホを持っている人は分かるだろうが、ネットインフラとスマートフォンの急速な普及と進歩が時間軸や生活環境を劇的に変えた。そのスマホ事情はもちろん日本だけの問題ではない。スマホの使用率は、むしろ日本は遅れているぐらいで、今年発表されたプレスリリースの調査では、日本人のスマホ使用率は64%、お隣、韓国では92%、世界で一番使用率の低いインドでは40%だが、人口が日本の約10倍あるので保持台数としては6倍以上。 アジアで後進国と言われていた国の人達は、僕たちが感じている以上に、時間軸や生活環境、教育が変化し,先進国以上のスピードで成長を続けている。 「全くもって、うかうかはしていられない」。 スマホの普及に合わせるようにメディアは姿を変えた。 今まではテレビ番組の録画といえば、テレビ台の下に大切に置かれたビデオデッキに新聞のテレビ欄を見ながらリモコンをポチポチと操作しながら番組ごとに録画していたものだ。たまに、プロ野球の延長で録画していた番組が見れなかったなんてことはなかっただろうか? それが今ではティーバというアプリを使うと、録画し忘れた番組(1週間限定)を好きな時間に見ることができるし、時間のない時はそれの方が効率的だったりする。 5年前、こんなことになるなんて思っていた人はいただろうか? そして、次の10年を想像することができる人はいるだろうか? だからこそ必要なのは対応力とスピード感覚。 「こんな田舎には関係ないだろう」とか 「田舎には変わらない魅力がある」なんて意見もあると思う。 僕も田舎が好きで移住してきた人間なので変わらないで欲しいことは一杯ある。 でも、人は周りの変化に対応していかなくてはいけない。 スピード感覚では村長選は馬場さんで決まりだろう。 対応力という面では小樽市は早かった。 昨年中に小樽議会はペーパレス化の検討を始め、先日は、小樽の小学生ひとりに一台のタブレットと中学生にはパソコンを年度内に行き渡せると新聞にあった。 ネットが当たり前の子供が将来大人になる。当たり前のことだがボヤボヤしていると「あっ」という間に時代に置いて行かれることになりかねない。今こそ変わらなくてはいけない。 新しい感覚を持ったリーダーの誕生と分析能力を持った手腕、その為にも今回の選挙は、変わることが一番大切だと信じてやまない。―――――「このままでいいとは思えない」 数日前のブログにも書いた通り、噂では、僕が怪我したことになっていたり、副村長になっていたりと、とんでもないデマが流され、「これが田舎の選挙なんだぁ」と、なんとも嫌な気になったものだ。 「やられたらやり返せ―――!(笑)」なんて思ってはいないが、ずいぶん心が弱くなるものだ。 そんな時に偶然手に取った本『凡人のための地域再生入門』(木下斉著)には、こんなことが書かれていた。 メディアはいつも「地方に移住した若者のサクセスストーリー」や「老人たちの心温まる物語」など、地方を綺麗に切り取ろうとします。しかし、実際には新たな取り組みを潰そうとする地方の権力者や、他人の成功を妬む住民、補助金情報だけで生活する名ばかりコンサル、手柄を横取りしようとする役人など、様々な欲望が渦巻いています。(少し簡略しました) これを読んで、どこにでもあることなんだと苦笑い。 そして、続きに 自分たちで何もせずに文句だけ言う人ばかりがいる地域が栄えた例は、歴史上ありません。 とも書いてある。 早いもので15年も前になるようだが、僕は当時の仲間と一緒にアリスファーム代表である藤門弘氏を村の議会に運ぶお手伝いをさせて頂いた。不満や文句は彼を通して議会に伝わったし、議会の情報も聞くことができて何となく安心していた。 4年前、「議会を三期、務めたので次の選挙には出ない」と知らされた時も、残念な気持ちになったが、今後のことをあまり深く考えようとしなかった。 でも、彼が辞めたあとの議会を知る限り、規律していた均衡が崩れ、議会の暴走がはじる。 今にして思えば、藤門氏が未然にブロックしてくれていたことを感じる。 ―――――「戦ってくれていたんだなぁ」と改めて感謝。 その後の4年は広報の『議会だより』と実際に行われた村(自治体)の政策でしか知りえない。 残念だが『議会だより』は一般質問と回答のみ。しかたがないのでその一般質問の数を取り上げてみた。 能登議員(1) 15回 23件 湯澤議員(1) 14回 17件 山口議員(6) 5回 6件 丸山議員(4) 3回 3件 川人議員(2) 1回 1件 安達議員(5) 0回 0件 竹下議員(1) 0回 0件 岩井議員(11) 議長なのでなし (当選回数) 一般質問に立った数 質問件数の順 議員の仕事は何も一般質問だけではない。特に行政から出された案件を採択したり、議案を審議して議決することがとても重要な仕事だ。だからこの数字だけで議員の評価にするつもりはないが、努力とやる気は計れるのではないだろうか? 特に一般質問は住民の声を拾い、住民の疑問に答えることに直結する。十数回一般質問に立った議員と一回も質問に立っていない議員の、どちらを支持するかと言えば、やはり、質問に立った方を僕は支持したい。 僕は噂やデマは信じないし、分からないのに人を悪く言うのはフェアーではないと思う。 この数字は実績なので21日の投票の参考にして貰いたい。 (一般質問の0回の議員は今回出馬を取りやめることになったので僕の目標はひとつ達成) では逆に、能登議員と湯澤議員は一期目にも関わらず、殆どの議会で資料を作り一般質問に立ったことは評価するべきだ。綺麗ごとで選挙は戦えないが、今回、僕が立候補することで二人の議員を落とすわけにはいかない。あくまで青臭く戦いたいのだ。 そこで悩んだ。とことん悩んで、悩んで考えたこと。 『 自分らしくやること 』 選挙期間中にできることは限られている。 村議選挙には戸別訪問は認められていないしチラシ(ビラ)は作ることができない。少ない人口のこの村で選挙カーを出して連呼して回ったり、個人演説も疑問だ。 認められていることは個別にハガキを出すこと、選挙ポスター、電話による投票依頼、そして、今回から認められたネットを使った選挙。 ―――――「ネット選挙!?連君、何人の人が読むと思うの〜?」 少なくとも僕のことを陰で悪く言う人は読まないだろうし、高齢の方で見る人は少ない。だからといって、これを見た人限定での選挙運動で勝ち目があるとは思えないが「今の議会ではダメだ」とか、「新しい感覚を持った人物を期待する」と言う人がいるなら、その人の心に届くことを願っている。 選挙運動は6日間。明日から終盤戦。自分のプロフィールや村へのアプローチに付いて書いてみたいと思う。 ここまで読んでいただいた方、残り2コマ(二日分)も読んで頂きたい。 付録1 仁木町の議会だよりが素晴らしい。一般質問の内容がわかり安く紹介されているし、議会で決まった事がどのように形になって行くかがわかり住民の意見や評価も紹介されている。ネットで検索して見ることができる。平成30年5月発行をリンクしたのでご覧いただきたい。 仁木町議会だより(PDF) 自分で書くプロフィールにどれだけの意味があるかわからないが、僕を手っ取り早く知ってもらうために、あらためて1ページを使って自己紹介をしたい。黒字はサッと読んで頂いて構わない。 普段心の支えにしている言葉がある。既に25年くらい前になるだろうか?生活に息づまるくらい必死で毎日を過ごしていた頃の年の瀬。紅白歌合戦の審査員として紹介された人間国宝の桂米朝師匠が、「ここまで長く続けられた秘訣は?」という質問に 「秘訣なんでありません。ただ一つお答えするなら、好きなことをやらせてもうて三度三度の食事を頂くことが有難いんです。毎日その繰り返しですがな、、、」と答えたとき、なぜか「ほっ」としたというか?こんな立派な人でも「その程度なんだ」と安心し、肩の力がゆっくりと下がったことを今でも鮮明に覚えてる。都会で育ち、満足な教育を受け、色々と人に支えられ、多くを求めていた自分の心を改め、その年の春から、身の丈をいつも意識しながら、自分の作る野菜に責任を持つ為『ひとり農業』を始め、何とか農業経営を続けられてきた。 学歴・職歴を書いておく 1978年 島根県立出雲高校入学(翌年、父の仕事の関係で転校) 1981年 京都府立西宇治高等学校卒業 1982年 国立東京水産大学入学(現東京海洋大学) 1986年 同校卒業 1986年 T&C航空サービス入社 1991年 退社(支店長代理) 1991年 赤井川村に移住し新規就農者として入村 2012年 赤井川整体院開院 家族は妻(順子)、長女(汐香)、長男(拓)の僕を含め4人と愛犬テン。だったが、子供たちはふたりとも独立、汐香は余市、拓は東京で不安定ながらも生活しているようだ。そして、夏は僕の父と母が同居。 赤井川村で農業委員を二期、統計調査員会長、赤井川中学校のPTA会長、畑かんの副会長、輪番だが区会長、農事組合長は何度かやらせて頂いた。 選挙運動は夜中の24時までできるらしいがブログはこの記事をもって最終回。ただ、このページは明日も回覧可能なので直前まで運動ができる。これはネットの良い点でもあるわけだ。 |